トマス・H・クック著 鴻巣友季子訳 文春文庫 1998年
池上冬樹がクックを大絶賛していた。偏見だと断って、「トマス・H・クックを知らない人は小説ファンではない。トマス・H・クックを読まずして現代小説を語ることはできない」と。池上冬樹が紹介する本も、私にとってハズレがないので読んでみた。期待以上だった。「複雑巧緻なプロットと切々たる哀愁の人間ドラマで読者を圧倒する」という、まさに。こういう本に出会えて至福だと思う。
小さな村の全寮制の男子校に若く、美しい女性教師が赴任してきたところから物語は始まる。裏さびれたバス停に緋色のブラウス姿で降り立ったエリザベス・チャニングを迎えたのは、チャタム校の校長と14、5歳の息子のヘンリー。ヘンリーの心と、校長の心にも、ミス・チャニングの姿が刻み込まれる。
ミス・チャニングは家を持たない主義の父親と小さい頃からアフリカやヨーロッパを放浪する。ヘンリーはそこに自由を見、その父親に傾倒する。ヘンリーの父親は、「忘れるな、大切なのは心だ」とヘンリーに繰り返し説いた。ヘンリーはそれを旧弊で煩わしいと思っていた。
ヘンリーは、「人生は愚に瀕してこそ、このうえなくうるわしい」というミス・チャニングの父親の言葉に心酔した。そして、年老いて思う。「これまでいかに軽はずみで浅はかな嘘を数々耳にしてきたにせよ、この言葉ほど罪深く、人を破滅にみちびく邪意にみちたものはない」と。
ミス・チャニングの父は自由というたいそうな主義をかかげていたが、それは娘への愛情のなせるわざではなかった。
ミス・チャニングは同僚の教師で、妻子あるレランド・リードを愛する。そこから「チャタム校事件」と呼ばれる未曽有の悲劇が始まる。
後年、ヘンリーの父は、ヘンリーに「チャタム校事件」に関する自らの知るすべてを話しながら、人の世のふしぎにとらわれていた。そこに張られたクモの巣の糸が、どれほど意地悪く、非道をきわめるか。
この場面を読みながら、中村文則の『私の消滅』(文藝春秋、2016年)を思い出した。人生に倦んだ医師は自らクモの巣の糸を織りなした。自らの楽しみのために。
最後の場面が一番好きだ。今まで読んだすべての本のなかで、一番好きな場面かもしれない。図書館で借りて読んだが、手元に置きたくて購入した。
「嘆きのピエタ」のなかで、三人が横たわっている場面で感じたのと同じもの。
「浄化」と「受容」。
ヘンリーの幼い故の高慢さ。そして、その高慢さが犯した罪。人生を積極的に生きるのではなく、その罪を反芻することに費やした人生。
取り返しのつかないことを、取り返すすべはない。「その後」をどう生きるかだけかもしれない。
「その後」の長い、長い年月を、ヘンリーは、自分が幸せになれるかもしれない可能性を捨てて生きたので、ただそれだけを抱えもって生きたので、最後に、「浄化」と「受容」が訪れたのだと思った。


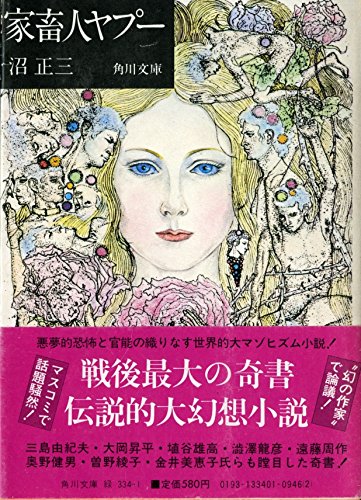
コメント