スヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチ著 三浦みどり訳
岩波現代文庫 2016年
第二次世界大戦でのソ連の死者は、2000万人(1941年~1945年)。日本のアジア・太平洋戦争の死者が軍民合わせて310万人だから、想像を超えている。
その戦いに、看護師や医師としてだけではなく、兵士としても、100万人を超える女性が従軍した。15歳から30歳だった。女性兵士のことは表舞台で語られることはなかった。
40数年後、スヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチはそれらの女性たち、500人以上から戦争体験の話を聞き、『戦争は女の顔をしていない』にまとめた。
1978年から2004年、30歳代で雑誌記者の時に取材している。1984年、第1稿を出版し、以後も取材を続け、2004年に最終稿を出している。日本では、2008年、群像社より刊行される。
アレクシェーヴィッチは、1948年、母の故郷ウクライナで生まれ、育ったのは父の故郷ベラルーシ。
2015年、ノーベル文学賞を受賞し、2016年来日している。この時のイベントで、「どうすればこれほどたくさんの人の心を開くことができるんですか?」と質問した小野正嗣は、「この小柄で物静かな女性がたぐいまれな〈耳〉の持ち主であることは確か」と書いている(朝日新聞2017年1月11日夕刊・いまこそ文学的聴力を)
「アレクシェーヴィッチが耳を傾けると、国家の大義やイデオロギーによって沈黙と忘却を強いられた人々が、それまで表現できなかった苦悩にふさわしい言葉を見出したかのように語り出す」
「他者の苦悶には耳を閉ざし、己の利得ばかりに執心する排他的態度が時代の空気になりつつある」日本の今とも繋がっている、と。
始まってすぐの戦争の悲惨さ、戦場での過酷な体験、スターリングラードの戦い。パルチザン、狙撃兵、工兵、通信兵、そして看護師として軍医として戦った具体的な記憶。
戦場で背が伸びたというまだ子どもともいえる年齢の少女たち。一日にして白髪になったという体験。
ドイツ軍による占領地での暴虐、虐殺。ドイツ軍は女性兵士を捕虜にはせず、残虐なかたちで殺したという。その語りに、心が凍る。中国における日本軍兵士と同じことをやっていたのだと知らされる。
そして戦勝後、女性兵士たちが故郷ソ連で受けた理不尽さ。
こうしたことが、時に涙とともに語られる。
「ありふれた生活から巨大な出来事、大きな物語に投げ込まれてしまった、小さき人々の物語」(以下、ランダムに抜粋)
〈女たちの戦争〉
「女たちの」戦争にはそれなりの色、臭いがあり、光があり、気持ちが入っていた。そこには英雄もなく信じがたいような手柄もない、人間を越えてしまうようなスケールの事に関わっている人々がいるだけ。そこでは人間たちだけが苦しんでいるのではなく、土も、小鳥たちも、木々も苦しんでいる。地上に生きているもののすべてが、言葉もなく苦しんでいる、だからなお恐ろしい……
女性の戦争についての記憶というのは、その気持ちの強さ、痛みの強さにおいてもっとも「強度」が高い。「女が語る戦争」は「男の」それよりずっと恐ろしいと言える。男たちは歴史の陰に、事実の陰に、身を隠す。戦争で彼らの関心を惹くのは、行為であり、思想や様々な利害の対立だが、女たちは気持ちに支えられて立ち上がる。女たちは男には見えないものを見出す力がある。
これは単に戦争というだけでなく、彼らの青春でもあった。
〈著者の姿勢〉
痛みに耳を澄ます……過ぎた日々の証言としての痛みに……そのほかの証言はない、それ以外の証言をわたしは信じない。
この人たちにもっと年が近かったら、わたしに対する態度も違っただろう。もっと冷静で、対等の話し方になり、若者と老人が会ったときの喜びはなかっただろう。これはとても重要な点。彼女たちが戦時には若かったこと、今は年老いて思い出しているのだということが。自分の人生の四十年をふりかえって、その世界をわたしに用心深く見せてくれる。
普段なら目に付かない証言者たち、当事者たちが語ることを通じて歴史を知る。そう、わたしが関心を寄せているのはそれだ。それを文学にしたい。しかし、語り手たちは証言者であるだけではない、証言者というよりもむしろ役者であり、創作者であったりする。リアリティに直接肉迫することができない。現実とわたしたちの間に気持ちがはさまる。それぞれの解釈を対象にしているのだということ、それぞれが解釈をもっており、それがたくさんあつまり、交差しあい、時代の、その時代を生きた人々のイメージが生まれる。
やめてしまいたい、脇道にはずれてしまいたい、というような迷いや不安の時があったがもうやめられなかった。悪というものにとりつかれてしまっていた。何か理解できるのではと覗き込んでしまったら、それは底なしの淵だったのだ。
〈実際の戦争〉
戦地では半分人間、半分獣という感じ。そう……ほかに生き延びる道はなかったわ。もし、人間の部分しかなかったら、生き延びられなかった。首をひねられちゃう。戦争では思い出さなければならなかった。何か……人間がまだ人間になりきるより前にあった何かを……
戦争で人間は心が老いていきます。戦後、私はもう決して若い娘に戻れませんでした。
戦争の映画を見ても嘘だし、本を読んでも本当のことじゃない。違う……違うものになってしまう。自分で話し始めても、やはり、事実ほど恐ろしくないし、あれほど美しくない。戦時中どんなに美しい朝があったかご存知? 戦闘が始まる前……これが見納めかもしれないと思った朝。大地がそれは美しいの、空気も……太陽も……
〈戦争の残虐さ〉
一番印象に残っているのは……生涯忘れられないのは……最初の年のこと、私たちが退却していく時のこと……。味方の兵士たちがライフルだけでドイツ軍の戦車に飛びかかっていったこと。銃床で装甲板をたたいているのを見たことよ。たたいて、わめいて、泣いてたわ、倒れるまで。ドイツ軍の自動小銃で撃ち殺されるまで。戦争の最初の年は戦車や戦闘機を相手にライフルで戦ってたのよ……
一番恐ろしかったのはスターリングラードだよ。~ スターリングラードには人間の血が染み込んでいない地面は一グラムだってなかった。ロシア人とドイツ人の血だよ。~ 補充兵がやって来る。若い元気のいい人たちが。一日二日でみんな死んでしまって、誰も残らない。~ 1942年のことだった。一番つらい、困難な時だった。三百人いたうち、その日の終わりには十人しか生き残っていないこともあった。
町の中を気の狂った女の人がさまよってました。その人は顔も洗わず、髪をとかしたこともありません。五人の子供を殺されたんです。全員。殺し方はいろいろでした。一人はアタマに弾丸をぶち込まれ、もう一人は耳に。~「あたしの子供がどんなふうに殺されたか話してあげるよ、~ 」みんな、その女の人から逃げていました。その人は狂っていたのです。だから話すことができたんです……
ファシストたちに切り落とされた脚が入ったままのブーツが塹壕の前に並べてあった。
累々たる屍が目に浮かぶ。開いた口が何かを叫んで、言い残したことがあるみたい。腸も飛び出している。薪の数よりもっと死体を見て来たよ。白兵戦の恐ろしさときたら、人間が人間に襲いかかっていくんだよ、銃剣を構えて。~ どんな顔してこういうことを思い出しゃいいのか? 話せる人たちもいるけど、私はできないよ……泣けてきちゃうよ。でもこれは残るようにしなけりゃいけないよ。いけない。伝えなければ。世界のどこかにあたしたちの悲鳴が残されなければ。あたしたちの泣き叫ぶ声が。
〈ユダヤ人差別〉
戦前はみな一緒に仲良く住んでいたのよ。ロシア人もタタール人もドイツ人もユダヤ人も、みな同じに。~ 町中に貼り紙があった。「ユダヤ人には次のことを禁ずる――歩道を歩くこと、美容院へ行くこと。店で何かを買うこと、笑うこと、泣くこと」
〈従軍した夫と妻の話〉
私(夫)のはもっと具体的な戦争の知識だ。彼女のは気持ちだ。気持ちの方がいつだってこういうことがあったという知識よりもっと強烈だ。
〈祖国愛〉
(スターリンに対して懐疑的だったが)「兄弟姉妹たちよ!」と呼びかけられたら、コロッとそれまでのくやしさを忘れてしまった。~ スターリンの演説のあとでおかあさんは言ったの、「祖国を守りましょう」って。みんなが祖国を愛していたわ。
私には聞こえた、言葉が……毒のある……その言葉は石のように……「戦いに行きたいなんて男が望むことだ、どこか異常だな、女じゃないな。何か欠けてるんだ……」そんなことないわ! 何千回でも否定できる。あれは人間として当然の望みだったわ。~ 隣の女の人は夫が負傷して、野戦病院に入院しているという手紙をもらった。~ 他にも片手を失った人、片足をなくした人が村に帰って来ていた。その人たちの代わりに誰が戦うんだろう? ~ わが国では私たち自身が関わらないですむことは何もない、国を愛するように、国を誇りに思うようにと、そう教え込まれていたんです。戦争が始まったからには、私たちも何か役立つべきだった。看護婦が不足なら看護婦になる、高射砲の砲手が足りなければ砲手になるだけのこと。
父は古参の共産党員でした。子供の頃から「祖国がすべて」と聞かされて育ちました。祖国は守らなければならない、と。全く迷いもなく、私が行かなかったら誰が行くだろうかと思ったんです。
あの頃の私たちのような人たちはもう二度と出てこないわ、決して。あれほど純真で、一生懸命な人たちは。あれほど深く信じ込んでいる人たちは。
大好きな父は、共産党員だったわ、清廉潔癖な人だった。~「ソヴィエト政権がなかったら、私はどうなっていたか分からない。貧民の子供で。富農の小作になっていただろう。ソヴィエト政権がすべてを与えてくれたんだ。教育も受けさせてくれた。そして技師になって、橋を建設している」私はソヴィエト政権が好きでした。スターリンが好きでした。父は私にそう教えたんです。~ 父のような人たちのことを愚か者だ、スターリンを信じてしまった盲目だと言う人たちがいますが、私はそうは思わない。誓って言いますが、あの人たちは、正直で善良な人たちだった。あの人たちが信じたのはスターリンでもレーニンでもなく、共産主義という思想です。人間の顔をした社会主義、と後によばれるようになった、そういう思想を。すべてのものにとっての幸せを。一人一人の幸せを。夢見る人だ、理想主義者だ、と言うならそのとおり、でも目が見えていなかった、なんて決してそんなんじゃありません。~ 戦争の半ばになってわが国にも素晴らしい戦車や飛行機、性能のいい兵器がでてきました。でも、信じるという力を持っていなかったら、強力で規律があって全ヨーロッパを征服してしまったヒットラー軍のような恐ろしい敵を私たちは決して打ち負かすことができなかったでしょう。~ 私たちの最大の武器は「信じていた」ということです。恐怖にかられてやったわけじゃありません。共産党員として誓いますが(私は戦争中に共産党に入党して、今も党員です)。党員証を恥ずかしいと思わないし、他の人たちのようにそれを捨てようともしませんでした。そういうことをした人の中に私の友人はたくさんいましたけれど。でも、私が信じていることは当時からほとんど変わっていません。1941年から……
〈戦争が終わって〉
祖国でどんな迎え方をされたか? 涙なしでは語れません……四十年もたったけど、まだほほが熱くなるわ。~ 女たちはこう言ったんです。「あんたたちが戦地で何をしていたか知ってるわ。若さで誘惑して、あたしたちの亭主と懇ろになってたんだろ。戦地のあばずれ、戦争の雌犬め……」ありとあらゆる侮辱を受けました……
誰にも自分たちが前線にいたことを言わなかった。~ 私たちが奉られたり、懇談会に呼ばれたりするようになったのはもっと後になって三十年もたってからのこと。~ 男たちは戦争に勝ち、英雄になり、理想の花婿になった。でも女たちに向けられる眼は全く違っていた。私たちの勝利は取り上げられてしまったの。〈普通の女性の幸せ〉とかいうものにこっそりすり替えられてしまった。
「ソ連の将校は降伏しない、わが国で捕虜になった者はいない、生き残った者は裏切り者だ」、同志スターリンはそう言った。~ 戦争中の四年間、そして、勝利のあともコルイマから戻るのを七年間息子と待った……ラーゲリ(強制収容所)からもどってくるのを。全部で十一年待ったんです。
私たちは地上に永遠の平和が訪れるような気がしていた。誰も二度と戦争を欲するものはない、武器兵器はすべて廃棄されるはずだ、私たちは憎むことに疲れてしまったんだから、弾を撃つことに疲れていたんだから。どんなに家が恋しかったか!
〈あるフランスの記者〉
(フランスでは)あなた方のことはほとんど知りません。多くの人がヒットラーに勝ったのはアメリカだと、そう思っています。ソ連の人たちがこの勝利のために払った犠牲、四年間で二千万人という犠牲はあまり知られていません。あなた方のあまりに非人間的な苦しみなど知らないんです。ありがとうございました。胸がつまります。


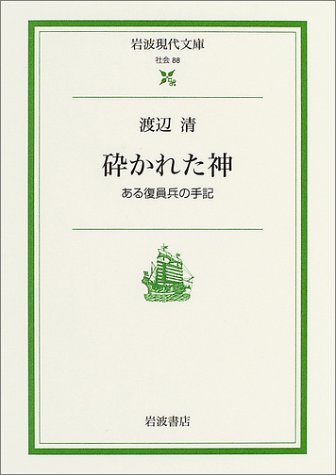
コメント