坂東眞砂子著 集英社 2011年
福島原発事故6ヶ月後に刊行された小説。
「ホラーサスペンス。集落の老人たちの穏やかさの衣に隠れた悪意」という紹介文を目にして、読みたくなった。(以下、結末の説明あり)
妻は放射能汚染から逃れるため、夫は定年後趣味の陶芸に生きるため、四国の山深い地にログハウスを建てる。住民は老人ばかりの閉鎖的な土地柄。
序章で、住民の一人の不審な死が描かれる。山の中で、右手に日本刀を持ち、左手は空(くう)を掴んでいた。
新参の夫婦が満足したのは春だけ。
夏には昔からの住民共用の道に陶芸窯を作ったことで、土地の老人たちから嫌がらせを受け始める。猫の死骸が畑に吊され、台風の時は水を引いている沢水のパイプが切られ水が出なくなる。
秋には嫌がらせはさらにエスカレートする。飼い犬も殺されたのか死んでしまう。
夫も妻も穏やかさを失っていく。特に妻は苛立ち、恐怖の中で神経をすりへらす。
夫婦の間も険悪になってくる。かつて息子が鬱になった時の夫婦の亀裂が蘇る。「おまえが息子をあんなにしたんだ」という言葉を投げつけられた妻。
「一度、心に深々と突き刺さった言葉の刃は、錆びて朽ちることなく、そこに残り続けている」妻は子育てに失敗したという負い目を自ら持った故に、自分を棚に上げて批判する夫が許せなかった。
そして冬。老人たちは毎年恒例の猪狩りを始める。
夫は窓ガラスを割られたので後を追って山に入る。妻も追いかける。いつの間にか、二人は猪狩りの老人たちに猟銃を持って追われている。
老人たちは二人を狩って、山頂の鳥の岩というところに追い込む。
老人たちも狂っている。崖から下に飛び降りろと、銃口を向けて囃し立てる。
妻は恐怖に喚きながら崖側ではない急斜面に転がり落ちて、木に引っかかって気を失っている。
夫がさらに、崖から飛び降りろと銃口を向けられた時、序章で不審な死を遂げた老人の親友の老人が日本刀を引っさげて現れ、狂った老人たちを警察に突き出すと一喝する。
狂った一人が小刀で斬りかかるが、日本刀でなぎ払われ腕から血が吹き出る。狂った老人たちは急斜面を転がるようにして逃げ出す。
夫は妻を助けて崖の上によじ登らせる。妻は日本刀を持った命の恩人を狂った老人たちの仲間と思い、驚愕して崖の下に突き落としてしまう。夫に人を殺したと責められているように感じて、妻は転がっていた小刀で、夫を刺し殺す。
終章では、老人たちが何事もなかったかのように祭りの準備のために、山の「くちぬい様」のお宮を掃除に行っている。その後、序章で殺された老人の妻がネズミ取りの粉末を持って、沢水の取水口の方に歩いて行くところで終わる。
鳥の岩の場面。思いもしなかった展開。
ネットの感想は後味が悪かったという評が多かった。一つだけコメディーのようだったというのがあった。
要約していて確かにと思えるが、読んだ直後は衝撃を受けた。妻の心の動かし方に共感していたので、そこまで妻は追い詰められ、壊れてしまっていたのかとおののいた。そして最後は、夫の対応に批判的になった。
妻が嫌がらせに対して神経をすりへらし、ヒステリックになっていく時、夫は妻の反応を考えすぎだと取り合わない。もう少し妻に寄り添えたら、あそこまで精神を痛めつけられないだろうにと思うが、夫の反応の方が普通なのだろう。
過敏な人間と鈍感な人間の違いなのか。現実世界でも鈍感な人間が、普通、一般的だと大手を振って歩いている。
鳥の岩での出来事、夫は妻を下から支えて押し上げる時、日本刀を持った老人のことを命の恩人だと一言でも説明しておかないと、妻が動顛するのはわかりきっている。妻を思うのなら、その一言がないのが不思議。
妻がその老人を突き落としてしまうのも当然のこと。さらに追い打ちをかけるように、「人を殺したぞ」などと言うか。「警察には黙っていて」と言う妻に、「偽証はできない」と言う夫。
この辺りが「コメディーか、これは」と言えるところだが、私は真面目にとって、夫に腹を立てた。妻が狂って、夫を刺し殺すのも当然だと思った。
どんなに錯乱しても壊れても、心から愛しいと思う人を殺してしまうだろうか。
今世の中に溢れている「誰でもよかった」という殺人も、狂った頭で許せないという思いを不特定多数の人に転化しているのかもしれない。
タイトルの「くちぬい」とは、今は口縄と言われている神様のことで、「口を縫う」という意味。
神様に口を縫われるので、その集落に都合の悪いことは、部外者には決して話さない、漏らさない。したがって、真相は闇に葬られる。


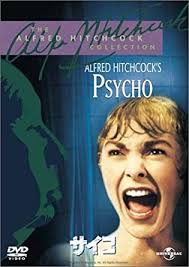
コメント