ヴァーツラフ・マルホウル監督 チェコ、スロヴァキア、ウクライナ 2019年
説明は一切ない。モノクロの映像。普通と言われる人々の苛烈な暴力。どこにでもある。普通の人々の集団が日本人にも見えて恐ろしかった。
最初は、10歳くらいの少年がなぜそんなに迫害を受けているのかわからなかった。ジプシーなのだろうかと思ったりしたが、途中で「ユダヤ人」とののしる声があったのでわかった。次にユダヤ人というのは外見でわかるのかと思った。大人のユダヤ人はある雰囲気があるので何となくわかる気がするが、黒い髪、黒い目がユダヤ人の証とか。日本人と一緒だ。
私はぼんやりなので、時代背景もわからなかったが、途中でドイツ兵やソ連軍、コサック兵などがでてきて第二次大戦下だと、やっとわかった。ウクライナ辺りかなとは最初の頃に何となく思った。
少年はユダヤ人狩りを恐れた両親によって田舎の叔母の家に預けられたのだ。ユダヤ人差別は東ヨーロッパの片田舎にも存在するのだと教えられた。映画では、舞台となる国や場所を特定されないようにインタースラーヴィクという歴史のある人工言語が使われている。
田舎の人々(子どもも含めて)のユダヤ人差別は激烈で、少年は話をしなくなる。ピアノを弾く場面があった。ここに来るまでは、穏やかで豊かな家庭で育ったのだろうと示唆する。
叔母も少年にやさしくはなかった。「自業自得」だと少年に吐き捨てる言葉に戦慄する。叔母が急死し、家が燃えて、少年は両親の元へと一人あてどなく向かう。
出会う人、出会う人が少年に悪意と邪悪と残虐のかぎりを尽くす。マルタ、オルガ、ハンス、……など、名前だけが画面に表示される。善き人に出会えることはあるのかと、画面を見つめる。
確かに少年を殺さなかったドイツ兵、少年の世話をしたソ連兵、助けようとした神父の存在はかすかな救いではある。しかし、それらの人々は善良ではあるが、少年の存在に対しては圧倒的に弱々しかった。
子どもに対する暴力は躾という名のもとに当時は普通に行われていたともいう。ヒットラーもすさまじい暴力を受けていたと、確かアリス・ミラーの本で読んだ。
少年は環境から学習し、生き残るために他人を排除し、損なうことも行えるようになる。そして、「目には目を、歯には歯を」と教えられたとおり、自らに屈辱と暴力を与えた者を、自らの手で殺すことさえできるようになる。
最後は迎えに来てくれた父親と出会う。一言も話さない少年は、父親を許せない。「自分の名前も忘れたのか」と泣く父親。やさしく、おとなしかった少年も少しだけ凶暴さを身につけている。
が、父親の腕に数字が刻まれているのを見て、父親が強制収容所に入れられていたのを理解する。曇ったバスの窓に自分の名前を書くことで、固い少年の心が少し溶けていくのがわかる。
原題は The Painted Bird(ペインティッド・バード)。ペンキを塗られた鳥という意味。小鳥を捕獲し、商売している男が、小鳥にペンキを塗って放してやる。小鳥は元の群れに帰るが、他の鳥たちは様子の違うその小鳥を皆で攻撃し、殺してしまう。象徴的な場面。放す男の残虐さ、邪悪さ、嗜虐性。男はそれを楽しみでやっている。
そして一方で、この男は、誰構わず性の相手を求める、精神を痛めた女性が女たちのリンチに遭い、殺されたのを嘆いて、自ら首を吊る。
(引っかかるものがあって、再度見直してみた。あとの展開を考えると、男は全くの楽しみでやったというわけではないかもしれない。小鳥は女にもらったものだった。女の奔放さと自分の無力さに絶望したうえでの当てつけのようなものともとれるし、女たちのリンチの予兆になっているとも言える。もちろん全体のテーマの象徴でもあるが。男の心がねじくれていたのだと思い直した。だから、女の死がなおさらにこたえたと言えるかもしれない。)
最初はペンキではなく、何か蜜のようなもので、鳥たちはそれを食べようとして放たれた鳥をつつくのだと思った。男の残酷さに震えがきそうだった。男の残酷さに変わりはないが、鳥たちが自分たちと違うから攻撃するという行動に救いがない思いだった。
「映画において、少年のような異物を攻撃する者は集団でやってくる。自分では何も考えず、善悪を見極める冷静な判断をなくした愚かな徒党は恐ろしい。自分がそんな渦にのまれて正しさを見失っていないか、足場を確認して日々を送りたいと改めて思う」という真魚八重子の映画評が心に残った。

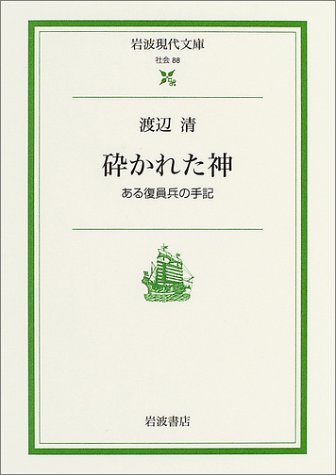

コメント