ロベルト・シュヴェンケ監督 ドイツ、フランス、ポーランド 2018年
「ドイツ敗戦まで1ヶ月。偶然に軍服を拾った若き脱走兵はナチス将校の威光をも手に入れた。――これは尋常ならざるサスペンスに満ちた驚愕の実話!」とチラシのキャッチコピーにある。
「エムスラントの処刑人」と呼ばれるヴィリー・ヘロルトは、1945年4月、ドイツ・オランダ国境近くの戦闘から脱走する。逃走中、大尉の軍服を偶然手に入れ将校になりすまし、多数の敗残兵を指揮下に収める。脱走兵や政治犯が収容されているエムスラント収容所アケシェンドルフ支所では、総統の命令と言い、支配権を手中にする。そして、囚人の拷問、処刑を行う。
ほぼ実話に基づいているという。大尉の軍服を身にまとい、嘘を吐く才能だけで、人々を服従させることができる。権力を手にした21才の若者は驚くべき残虐さを発揮する。
後味の悪い映画だった。
人間の悪意をあぶりだしていて、それが事実として坦々と描かれていて、とても不快な気分になる。現実にあり得ること、似たようなことはどこでも起こり得る。そのどす黒さと逡巡のなさに耐えきれないのか。
一人善良な人間、良心の呵責を感じていた人間も殺すことを強制され、そして殺してからは、徐々に暴力を振う人間へと変貌し、最後は率先して暴力を振う側の渦中にいる。それが現代にも繋がっていることを画面は見せる。
権力を振う人間とそれに追随する人間。嘘を吐いてでも権力を振う人間は確かにいるだろうが、そうざらにいるとは思えない。しかし、それに追随する人間はどこにでもいる。普通の私たちがそうである。軍服という権威に簡単に騙される。そして、その権威に同調する。
人間が生来持っている悪を増大させるものとは何なのか。そういう視点からみたら、示唆に富む映画と言えるだろう。小さなヒトラーはどこにでもいる。私たちの内部にいると示唆していて、不快な気分になってしまうのか。
悪に追随するのを拒絶できるものを、強さではなく、弱さのなかから培うにはどうしたらいいのだろうか?


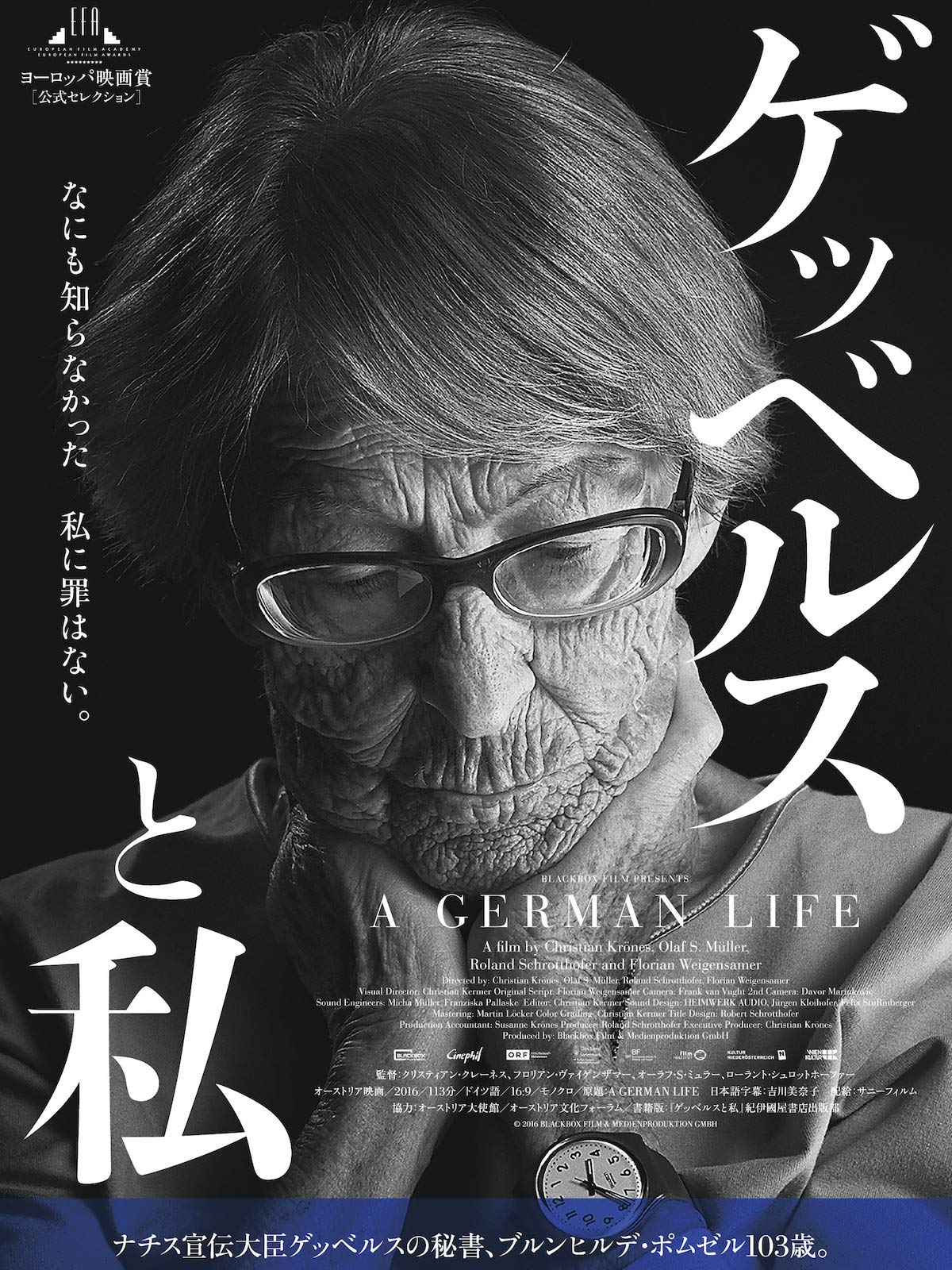
コメント