島本理生著 文藝春秋 2018年
女子大生による父親殺しというセンセーショナルな事件。父親は高名な画家。なぜ殺されたのか? その家庭では何が起きていたのか?
聖山環菜は女子アナを目指していたが、テレビ局の二次面接で倒れ、会場を去る。その足で、包丁を買い、父親が講師を務める美術学校に行き、父親を刺し殺す。
環菜に関して、本を書くよう出版社から依頼されている、心理療法士の真壁由紀。刑務所で面会を重ねている。由紀も実家の親との間で問題をかかえ、自分がサバイバーだと自覚していた。夫の我聞と小学4年生の正親と暮らしている。
10年前、我聞は前途有望な報道写真家で、小さな賞をいくつか獲得し、個展を開く準備も進めていた。由紀は大学院の修士論文を書いていたが、予期せぬ妊娠が分かり、堕ろすつもりだと言い終わらないうちに、我聞は「僕の夢なんていいよ。子供だったら僕が育てるから、結婚しよう」と言い、二人は結婚する。
環菜の弁護士を務めている庵野迦葉は、我聞の義理の弟で、8歳の頃に母親に捨てられ、餓死寸前で助けられた。母親の姉夫婦(我門の親)に預けられ、大事に育てられる。
迦葉と由紀は同じ大学の同期生で、同じ雰囲気を持つ似たもの同士。互いにかけがえのない存在だったが、傷つけ合った過去を持っている。今回、偶然協力関係を持つようになり、過去は封印して環菜の生い立ちや家庭、交友関係などを調べる。
その過程で、小学校高学年から中学にかけて、環菜が父親の主催するデッサン会でモデルをしていたことが分かる。そこでは、彼女自身は服を着ていたが、ヌードの男性と背中合わせに何時間も座っていたことが明らかになる。そして、母親は幼い環菜を守ることはしなかったということも。由紀は環菜に昔の自分を重ねる。
環菜は事件について、「私のせいなんです。私が全部悪いんです」と思っている。
環菜の母親は、環菜を嘘つきだと言う。そして、検察側の証人になり、環菜に対してことごとく責任を回避するような言動をとる。それはかえって巨大な闇が潜んでいるように、由紀には感じられる。
環菜は母を責めないでくださいと、由紀に言う。しかし、母親が環菜のことで嘘をついていたことが分かり、環菜は母親の支配に抵抗する。私が嘘をつくことで、母は安心していた、と告げる。
そして、事件は故意ではなく、事故だったと主張する。ここまできて、殺人から事故にかえるのは、裁判上不利になると弁護士として迦葉は思うが、それでも迦葉も由紀もそれが環菜にとって真実なら、それを貫くしかないと、環菜を支える。
検察側の尋問に、考えながら落ち着いて話す環菜を見て、由紀は環菜が自分の言葉を獲得したと思う。
判決は、事故という主張は認められなかったが、懲役15年の求刑が懲役8年となっていた。
性的虐待とネグレクト。
環菜を見ていて、そして自らを顧みて、由紀は思う。
「さかのぼって原因を突き止めることは、責任転嫁でもなければ、逃げでもない。今を変えるためには段階と整理が必要なのだ。見えないものに蓋をしたまま表面的には前を向いたようにふるまったって、背中に張り付いたものは支配し続ける」
「納得いかない理由を押しつけられた記憶や理不尽は死ぬまで残る」、と。
「抱え込んでいた闇に光が当たる時、人は、もう一度、生まれることができる」という体験をした由紀は、裁判を通して、環菜もそうあってほしいと願い、そしてそれは満たされるだろうと思う。
環菜は裁判が終わった後、次のような手紙を由紀に送っている。
法廷で、大勢の大人たちが、私の言葉をちゃんと受け止めてくれた。
そのことに私は救われました。
苦しみ悲しみも、拒絶も自分の意思も、ずっと、口にしてはいけないものだった
から。
どんな人間にも意思と権利があって、それは声に出していいものだということ
を、裁判を通じて私は初めて経験できたんです。
『放蕩記』(村山由佳著、集英社文庫)の解説で、島本理生は「もし夏帆が温かい気持ちで、美紀子に理解を示して心を開いていたら。たぶん美紀子は夏帆に全面的に依存し、孤独やフラストレーションをぶつけて同一化しようとしただろう。そうしたら夏帆の心や人格など踏み荒らされた庭も同然である。自分を壊そうとするものを無防備に侵入させるわけにはいかない」と書いていた。自分自身に照らして、苦い気持ちで読んだ。そして、島本理生の作品を読んでみたいとずっと思っていて、やっと叶った。期待に違わなかった。
親との関係で心を病む、生きづらさを抱える、何かしら歪んだ世界を生きざるをえない人生を押しつけられる、この理不尽さに苛立ちと怒りを募らせる。こういう世界をミステリー風にうまく描ききったなと思った。
直木賞、受賞作。

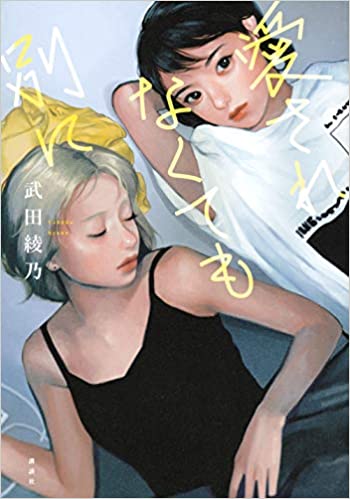

コメント